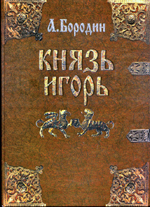歌劇『イーゴリ公』
「だったん人の踊り」で有名な歌劇『イーゴリ公』とは、一体どんなオペラなのでしょうか?
作者
| 台本 |
アレクサンドル・ポルフィーリェヴィチ・ボロディン
『イーゴリ遠征物語』
のオペラ化を企画したスターソフが台本の原案を作成し、
それを元にボロディン自身が作詞をしました。
第3幕は、リムスキイ‐コルサコフが作詞しています。 |
| 作曲 |
アレクサンドル・ポルフィーリェヴィチ・ボロディン
ボロディンの死後、リムスキイ‐コルサコフとグラズノフが補筆、
オーケストレーションを行いました。
(序曲はグラズノフの作曲です。) |
初演
| 日時 |
1890年11月4日(旧暦10月23日) |
| 場所 |
サンクト・ペテルブルク、マリインスキイ劇場 |
| 指揮 |
カルル・クチェラ |
| バレエ振付 |
レフ・イヴァノフ |
舞台背景(初演版)
時代
|
1185年 |
場所
|
プロローグ、第1幕、第4幕 / プチーヴリ
(現在はウクライナにある都市)市内
第2幕、第3幕 / ポーロヴェツの陣営 |
登場人物
イーゴリ
(バリトン) |
主人公。
ノーヴゴロト・セーヴェルスキイの領主。 |
ヤロスラーヴナ
(ソプラノ) |
イーゴリ公の二度目の妻。
ガーリチ公女。 |
ヴラヂーミル・
イーゴリェヴィチ
(テノール) |
イーゴリの先妻との息子。
プチーヴリの領主。 |
ガーリチの
ヴラヂーミル・
ヤロスラーヴィチ
(ハイバス) |
ヴラヂーミル・ガーリツキイとも。
ヤロスラーヴナの兄。 |
コンチャーク
(バス) |
ポーロヴェツの長(ハーン、汗)の一人。
イーゴリ公の身元引受人。 |
コンチャコーヴナ
(コントラルト) |
コンチャークの娘。
劇中では名を呼ばれることはなく、姫(公女)と呼ばれる。 |
オヴルール
(テノール) |
キリスト教徒のポーロヴェツ人。
イーゴリの脱走を手引きする。 |
スクラー
(バス)
イェローシカ
(テノール) |
グドーク弾きの狂言回し。 |
ヤロスラーヴナの乳母
(ソプラノ) |
|
ポーロヴェツの娘
(ソプラノ) |
|
物語(初演版)
●プロローグ
<プチーヴリの広場>
イーゴリ公の先妻の子、ヴラヂーミルの領地、プチーヴリ。
この町からイーゴリ達、4人の公はポーロヴェツの侵入を防ぎ、ルーシ(南ロシヤ−現在のウクライナ−に住んでいた東スラヴ人の国の呼称)
を守るために遠征しようとしている。
いざ出陣という時に日食がおこる。イーゴリの後添えであるヤロスラーヴナは不吉だから出陣するなと懇願するが、
イーゴリはヤロスラーヴナの兄、ガーリチのヴラヂーミルに後を託してプチーヴリを後にする。
●第1幕
<第1場・ガーリチ公の館の中庭>
イーゴリ達の留守中、プチーヴリを任されているガーリチのヴラヂーミルは郎党を引き連れ、
昼日中から酒に浸っては町の娘をかどわかすような横暴を繰り返していた。
ヴラヂーミルはもし自分がプチーヴリの主だったら、贅沢三昧、美女をはべらせ思うままに支配するのに、と豪語し、
さらわれた娘を解放するようにと請願に来た町の女達をも追い返す。
ヴラヂーミルを支持する男達は、彼をプチーヴリの公にしようと怪気炎をあげる。
<第2場・ヤロスラーヴナの館の居室>
出陣していったイーゴリ達の無事を願うヤロスラーヴナの元に、町の女達がガーリチのヴラヂーミルの横暴を訴えにやってくる。
そこへヴラヂーミル本人が現れ、イーゴリのいない今、プチーヴリの支配者は自分だ、とヤロスラーヴナを脅す。
苦悩するヤロスラーヴナの元に、貴族達がイーゴリ達の敗報とポーロヴェツ軍の来襲を伝えにやって来る。
●第2幕
<ポーロヴェツの陣営>
イーゴリ達が捕らえられているポーロヴェツ人の陣営では、イーゴリの息子ヴラヂーミルとコンチャークの娘が恋仲になり、将来を誓い合う。
一方、イーゴリは遠征軍を壊滅させ虜囚の身になった己の不甲斐なさをかこち、妻の身を案じ、自由でさえあれば再びルーシのために戦うのに、と苦悩を吐露する。
ポーロヴェツ人でありながら、キリスト教徒である若者オヴルールがイーゴリの闘志を鼓舞し、脱出の機会を待つよう彼に告げる。
しかし、イーゴリの武人としての矜持が逃亡という行為を許せず、決意を固めることができない。
イーゴリ達を捕らえているポーロヴェツ人の長、コンチャークはイーゴリ達を虐待することなく、むしろ豪胆かつ寛大にもてなす。
コンチャークはイーゴリにルーシを裏切り、自分達にくみするようにと説得するが、イーゴリは待遇に謝意を表しつつもコンチャークと手を組むことは断固拒否する。
イーゴリの武人としての態度に惚れこんだコンチャークは急遽宴席を設けさせ、奴隷達に歌舞を披露させる(だったん人の踊り)。
●第3幕
<ポーロヴェツの陣営>
ポーロヴェツ人の別の長、グザークとその一隊がルーシの町々を略奪して凱旋して来る(だったん人の行進)。
コンチャーク始め、ポーロヴェツ人達が勝利に酔う一方で、囚われのルーシの人達はイーゴリにここから逃亡してルーシに帰り、祖国を滅亡の危機から救って欲しいと懇願する。
脱走の決心を固めたイーゴリはオヴルールに手はずを整えさせる。
共に逃亡するはずであるイーゴリの息子ヴラヂーミルの元にコンチャコーヴナ(コンチャークの娘)がやって来て、ここに留まるか、さもなくば自分も連れて行くようにと哀願する。
イーゴリはヴラヂーミルには行動を共にするよう、コンチャコーヴナにはヴラヂーミルを行かせるように説得するが、二人は離別を受け入れることができない。
脱走の頓挫をおそれたイーゴリはついに一人でその場を去り、ヴラヂーミルも脱走するのではないかと危惧したコンチャコーヴナは警報を鳴らしてしまう。
イーゴリの逃亡が発覚し、ポーロヴェツ人達はヴラヂーミルを処刑しようとするが、コンチャコーヴナがそれを許さない。
その様子を見てコンチャークはヴラヂーミルを娘婿に迎え、明日ルーシに出陣すると一同に言い渡す。
この第3幕は台本をリムスキイ-コルサコフが書き、音楽も大部分をリムスキイ-コルサコフとグラズノーフが担当しているため、
多くの場合上演の際に省略されます。
●第4幕
<プチーヴリの城壁と広場>
プチーヴリではイーゴリの妻ヤロスラーヴナが城壁にたたずみ、帰らぬ夫とその軍が惨敗した戦に思いを馳せて嘆いていた。
ポーロヴェツの略奪によって疲弊した農民達が歌いながら通り過ぎていく。
その様子を眺めていたヤロスラーヴナは、こちらへと馬を走らす二つの人影を認める。イーゴリとオヴルールである。
二人のグドーク弾きが鐘を鳴らしてイーゴリの帰還を町中に知らせ、人々はイーゴリの帰還を喜び祝う。
歌劇『イーゴリ公』の初演版全曲の構成(各曲の作曲年、作曲とオーケストレーション担当者)を一覧にまとめました。
上のリンクからどうぞ。(2018/07/25)
オーケストラの楽器編成
●木管楽器
ピッコロ×1、フルート×2、オーボエ×2、
イングリッシュホルン×1、クラリネット×2
バスクラリネット×1、ファゴット×2
●金管楽器
ホルン×4、トランペット×2、トロンポーン×3、テューバ×1
●打楽器
ティンパニ、グロッケンシュピール、トライアングル、スネアドラム
ドラム、シンバル、バスドラム、第1タムタム、第2タムタム
●編入楽器
ハープ、(任意にてピアノ)
●弦楽器
第1ヴァイオリン×16〜20、第2ヴァイオリン×14〜18、
ヴィオラ×10〜14、チェロ×8〜10、コントラバス×8〜10
●舞台上
コルネット×2、アルトホルン×2、テノールホルン×1、
テューバフォーム(バリトン)×1、テューバ×1、スネアドラム×1
この楽器編成は次の項目でご紹介しているベリャーエフ社版の楽譜に拠っています。
数字の指定がない楽器は1台、または1組です。(2011/11/02)
楽譜(初演版)
歌劇『イーゴリ公』全曲のヴォーカルスコアをご紹介します。
| ベリャーエフ社版(フランクフルト) |

|
1980年発行
初演版
ドイツ語・フランス語・ロシア語による歌詞併記 |
1888年にリムスキイ-コルサコフらにより、初演に先駆けて出版されたオリジナル版です。
ここでご紹介している版は1980年発行のものですが、スコアそのものは100年近く改版されていないかも知れません。
併記されているロシア語は100年前の正書法によるものです。
ドイツ語の正書法も近年改正されましたので、これまた古いものです。 |
| ムズィカ社版(モスクワ) |
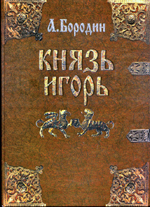
|
2003年発行
初演版
ロシア語による歌詞併記 |
本国ロシアで発行された全曲のヴォーカルスコアです。
ベリャーエフ社版と較べてやや大判ですが、スコアは小さめになっています。
補筆、編曲に携わったリムスキイ-コルサコフやグラズノフらの名前は明記されていません。
併記されている歌詞は現行の正書法によるロシア語です。 |
『イーゴリ公』ア・ラ・カルト
歌劇『イーゴリ公』にまつわる様々なエピソードを集めてみました。
未完の歌劇『イーゴリ公』
「イーゴリとコンチャーク、好敵手ともいうべき二人のその後は?」
「プチーヴリに戻ったイーゴリは再度遠征に出たのか?」
「イーゴリが戻ってきて、ガーリチのヴラヂーミルはどうなったのか?」
上記の物語をお読みになって、このような疑問を持たれた方も多いと思います。しかし、これらの疑問には作品の上では答えがありません。
それには二つの理由があります。
一つは、出典となった『イーゴリ遠征物語』も史実も、イーゴリ率いる遠征軍の大敗と一度は怪我をし囚われたイーゴリがルーシに無事に帰還する、という内容であり、
英雄譚としてはやや盛り上がりに欠けること、もう一つは、作詞(台本)作曲に携わったボロディンが18年を費やしながら、どちらも未完成のままでなくなったことです。
ボロディンが残した『イーゴリ公』は上述と重複しますが、ピアノ譜、オーケストラ譜、グラズノフが暗譜していたメロディーと、完成の度合いもまちまちで、
ボロディンの手稿をもとにリムスキイ‐コルサコフがオーケストレーションと第3幕の台本を手懸け、グラズノフが序曲を作曲しました。
こうして上演できる形に仕上げられたのが、いわゆる初演版です。
「だったん人の踊り」と『イーゴリ公』がポピュラーなタイトルとして私たちが楽しむことができるのは、間違いなくリムスキイ‐コルサコフとグラズノフの功績といえるでしょう。
ただ、この初演版には物語の起伏の乏しさ、いくつかの解決されずに残される問題、そのためにぼやけてしまう主題、といった台本に現れる問題と、
ボロディンのオリジナルのメロディーとリムスキイ‐コルサコフ、グラズノフの補筆したメロディーとの相違、といった譜面に現れる問題があり、
現在では上演される際には新たな解釈、アレンジが加えられることが多いようです。
『イーゴリ公』の聴きどころ
ロシア管弦楽曲集的なオムニバス盤によく収録されていて、様々なメディアを通じて聴く機会があるのは、
やはりなんと言っても「だったん人の踊りと合唱」でしょう。
次いで、収録されている機会が多いのが、「序曲」や「だったん人の行進」あたりではないでしょうか。
演奏会では、イーゴリやコンチャーク、ガーリチのヴラヂーミル、そしてヤロスラーヴナの独唱が歌われることがあります。
逆に全曲盤でしかほとんど聴く機会がない聴きどころとして、プロローグの「プチーヴリの民衆の合唱」や、第1幕の「女達の合唱」、
第4幕の「農民たちの合唱」等、印象的なメロディーの混声合唱がお薦めです。
是非、『イーゴリ公』のハイライトをコンサート形式ででも演奏する機会を作って欲しいと思いますし、ハイライト盤も録音・発売して欲しいと思います。
知られざるガーリチのヴラヂーミル
時として、架空の人物扱いされているヤロスラーヴナの兄、ガーリチのヴラヂーミル(ヴラヂーミル・ガーリツキイ)ですが、彼は実在しており、
やはり放蕩三昧で歴史に名を残した人物で、1187年の父ヤロスラーフの死後、実弟と争った後にガーリチに君臨したようです。
劇中では、ヴラヂーミル公、ガーリチ公(ガーリチからいらした公、ガーリチ出身の公)などと囃されていますが、
ヤロスラーヴナの「ガーリチの父上の元に送還させる」という台詞から、当時のガーリチを治めていたのは、二人の実父のヤロスラーフ公であることがわかります。
(この時代の公(侯)は位というよりは身分を表すもので、リューリクの子孫の成人男子はみな公(侯)と称していました。)
また、この人物は原作ともいうべき『イーゴリ遠征物語』には登場しません。
スターソフの企画で登場していたのか、ボロディンが独自に登場させたのか、定かではありませんが、
野心家である彼の存在がイーゴリの帰還を待望させ、イーゴリの不名誉を隠す効果を果たしているようです。
時として、コンチャークと共に主人公をくってしまうこともままありますが。
(白水社の『新グローヴ・オペラ事典』によると、ガーリチのヴラヂーミルは原案では史実に反して劇中で亡くなることになっていたようです。)
知られざるコンチャーク
イーゴリの男気を高く評価し身元引受人となり歓待し、また、イーゴリの息子ヴラヂーミルの命を救い娘婿に迎えたポーロヴェツ人の長(ハーン、汗)、コンチャーク。
勿論実在する人物であり、イーゴリと戦った人物ですが、実はコンチャークとイーゴリとはこの遠征が初対面ではなく、
遠征の5年前、1180年にはなんと二人は同盟を結んで当時のキエフ大公と戦っています。
第2幕、「だったん(ポーロヴェツ)人の踊りと合唱」の前にコンチャークがイーゴリにしきりに手を組もうと説得し、歓待する一方で、
イーゴリが頑なにそれを拒み、謝意を表しつつも闘志を奮い立たせる場面があります。
ともすると、コンチャークの親しげな態度と、イーゴリのよそよそしい態度に不可解な温度差を感じる場面でしたが、
二人が知己であり、コンチャークは戦友として、イーゴリは敵として相手と接していると考えると、すっきりと腑に落ちる場面になります。
絵で見る『イーゴリ公』
ヴァスネツォフ
絵本画家じゃない方のヴァスネツォフです。
おそらくカヤーラ河畔の戦場を描いています。死屍累々。
ヴァスネツォフは他にも英雄叙事詩ブィリーナを題材にした作品も描いています。
中世の武士が彼の絵心を刺激したのでしょう。
ビリービン
ロシアのミュシャとでも言うべきビリービンも1930年代にパリ、シャンゼリゼ劇場での上演用に、
『イーゴリ公』の舞台美術、衣装を手がけています。
このサイトで使用しているイラストレーションがそれです。
メディア
TVドラマを始め、様々なメディアで取り上げられた『イーゴリ公』を集めてみました。
(2020/04/02)
お茶になった『イーゴリ公』
フランスのお茶の老舗、マリアージュ・フレールさんのお茶に「T940 プリンス・イゴール(プランス・イゴール Prince Igor)」
という銘柄があります。
セイロン茶と日本茶のブレンドに、柑橘類等の花の香が調合されたフレーヴァー・ティー。甘い香りとすっきりとした飲み口の爽やかなお茶です。
このお茶に「イーゴリ公」の名がつけられた経緯は残念ながら不明ですが、
他にも「アイーダ」、「パルシファル」、「オペラでのお茶」といった名前の銘柄が並んでいるので、オペラ好きの店主さんがいらっしゃるのかも知れません。(2006/12/16)
グドークとグースリ
ロシアの伝統的な楽器と言えば、バラライカが有名ですが、
劇中に登場する狂言回し、スクラーとイェローシカが演奏しているグドークもグースリと共にロシアを代表する古い弦楽器です。
グドーク
グドークはリュートのような胴と長い首を持った3弦の楽器で、肩にかつがずに、弓で演奏します。
グースリ
一方のグースリは三角形に近い台形の琴状の多弦楽器で、膝に乗せて両手で爪弾きます(演奏用の爪を使用するのかどうかは不明)。
『イーゴリ遠征物語』に現れる伶人や、『ブィリーナ』のサトコーが演奏しているのは、グースリの方になります。
『イーゴリ公』のロシア語
『イーゴリ公』をロシア語で見たり、聴いたり、読んだりして、気付いたことを少々書いてみたいと思います。
正書法
『イーゴリ公』の台本は1870〜1880年代に書かれました。
ロシアの文学界ではドストエフスキイ、ツルゲーネフ、トルストイといった作家達が続々と写実文学を発表していた時代です。
この頃のロシア語は現代では用いられない文字が使われていたり、語の綴り方が古風だったりする、ロシア革命以前の正書法で書かれています。
現在入手可能なベリャーエフ社の楽譜に書かれているロシア語の歌詞もこの古い正書法で書かれています。
文体
古い正書法で書かれている『イーゴリ公』ですが、使われている言葉自体は基本的に120〜130年前のロシア語、しかも話し言葉なので、
現代のロシア語の知識が通用します。
ただし、要所要所に古典文学である『イーゴリ遠征物語』からの引用があり、古語がちりばめられています。
日本語に無理やり喩えるなら、旧字旧仮名の文章で古めかしいものの生き生きとした会話文の中に、
時々「心は猛う思へども、軍にはし疲れぬ、手負うつ」などと古文や古語が混じっている文体、と喩えることができるのではないでしょうか。
音節と綴り
『イーゴリ公』は歌劇、台詞は歌詞ですので、
生き生きとした話し言葉を基調とした台詞でも、歌われる際にリズミカルに音節を整えられることがあります。
これには母音を加える場合と母音を減らす場合があります。
母音を加えて音節数を整えている例として、プロローグの中から一例を紹介します。
Млад Володимиру да на Путивле,
млад соколику князю Владимиру,
上の行はプロローグ開幕の最初の合唱の中の一節、下の行はプロローグの最後の合唱の一節ですが、どちらも11音節で成立しています。
Владимир の与格の正しい綴りは下の行の通りですが、上の行ではこのままでは音節が足りないため、
Володимиру として、母音 о を加えています。
また、母音を減らして音節数を整えている例として、
А где ж наша рать?
А где же наш князь?
これは第1幕終盤のヤロスラーヴナの歌詞で、一続きに歌っている部分です。
ここでは上下とも5音節に揃えるために、 же という1音節の語の母音 е を落としています。
(上の行は、本来の же という形のままでは6音節になってしまいます。)
アクセント
ロシア語ではアクセントのある母音は長めにはっきりと発音され、アクセントのない母音は短く曖昧に発音されます。
また、疑問詞のない疑問文と平叙文の区別はイントネーションで区別し、英語やドイツ語のような語順の倒置を用いません。
このようなロシア語の話し言葉の特徴は歌にも反映される傾向があり、ムソルグスキイらも歌曲や歌劇で、
ロシア語のアクセント(リズム)とイントネーション(メロディ)を生かした作曲法を成立させました。
ボロディン(『イーゴリ公』)の場合は曲が先にあって、それに歌詞を載せていった印象があります。
第1幕のおどけたグドーク弾き二人組みの歌詞を例として挙げます。
Ой, хочу к батюшке,
ой, хочу к матушке,
話し言葉では下線を引いた部分がアクセントのある母音で、長めに発音されます。
(オーイ、ハチュー クバーチュシケ、オーイ、ハチュー クマートゥシケ、)
これがイーゴリ公では、2、444444、2、444444、と表現され、(2は二分音符、4は四分音符、44はスラーです)
話し言葉とはかなり違った印象を受けます。
(オーーイ、ハーチュクバーーチューシケー、オーーイ、ハーチュクマーートゥーシケー、)
2人称
ロシア語を学んだことのあるかた、またドイツ語やフランス語などを学んだかたにも馴染み深い現象だと思いますが、
現代ロシア語には2人称の人称代名詞に単数と複数の区別の他に、「親称」と「敬称」の区別があります。
2人称の人称代名詞тыは、常に話す相手は一人で、しかも相手が家族や親しい友人、親しい仲間内、そして子供と神様に限られます。
そのため、тыは「親称」の2人称と言われます。
もう一つの2人称の人称代名詞выは話し相手が2人以上の場合と、相手が一人でも心理的に距離がある場合(初対面の相手など)に用いられ、
「敬称」の2人称と呼ばれます。
面白いことに歌劇『イーゴリ公』では常に、一人を相手に話す時にтыを用い、
二人以上を相手に話すときにвыを用いています。
つまりтыとвыは単数と複数の違いだけを示し、「親称」と「敬称」の違いを表現してはいないのです。
2人称を「親称」と「敬称」とで使い分ける現象は、古代ギリシア語やラテン語には見られない比較的新しい時代に生じたものなので、
意識的に「敬称」の2人称の使用を避け、古めかしい雰囲気を出したのかもしれません。
人名
現代のロシアでは例えばアレクサンドル・ポルフィーリェヴィチ・ボロディンという人を呼ぶ時に、
выを使う改まった間柄なら「アレクサンドル・ポルフィーリェヴィチ」と呼び、
тыを使う親しい間柄なら「サーシャ」等と愛称で呼びます。
『イーゴリ公』の時代がどうだったのか、実際のところはわかりませんが、
歌劇の中では夫婦や兄弟、恋人同士の間柄でも「イーゴリ」、「ヴラヂーミル」と呼び合っていて、
ロシア語話者には微妙な違和感・非日常感があるかも知れません。
ちなみにスクラーとイェローシカという名は「イーゴリ」や「ヴラヂーミル」のような個人名ではありません。
スクラーは「頬骨」を意味する単語なので、もしかしたら「赤ら顔」、イェローシカは「ぼさぼさ頭」という意味の身体的特徴からつけたあだ名のようです。
Copyright(C)2006-2026 Vindobona. All rights reserved.