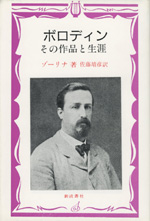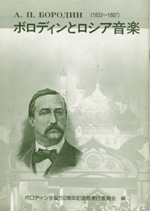年/月/日
(満年齢) |
|
1833/11/12
(0) |
アレクサンドル・ポルフィーリェヴィチ・ボロディン誕生。
実父、ルカ・スチェパーノヴィチ・ゲディアノフ(ゲデヴァニシヴィリ)公爵、
母、アヴドーチヤ(エヴドキーヤ)・コンスタンチノヴナ・アントノヴァ。
アヴドーチヤがゲディアノフ公爵の正妻ではなかったため、父の従者、ポルフィーリイ・ボロディンの息子として届けられた。 |
1842〜43頃
(9) |
ピアノ連弾用 ポルカ『エレーヌ』作曲。
少年時代、家庭で音楽と語学を学ぶ。
楽器はフルート、次いでチェロを楽しんだ。 |
1850/11
(17) |
医科大学薬学科入学。
メンデルスゾーンの影響を受けた室内楽曲の習作を書く。 |
1852〜53頃
(19) |
ピアノ連弾用 スケルツォ・ニ短調作曲。 |
1856
(23) |
3月、医科大学卒業、第二陸軍病院に勤務。
引き続き、「ロシア化学の祖」と言われるジーニンに師事。
陸軍士官のムソルグスキイと知り合う。 |
1858/5
(24) |
医学博士学位取得。 |
1859
(26) |
留学生として、ドイツ・ハイデルベルクに派遣される。 |
1860〜61
(27〜28) |
チェロソナタ、弦楽6重奏曲、ピアノ3重奏曲、ピアノ5重奏曲作曲。 |
1861
(28) |
5月、留学中のハイデルベルクで結核療養のために保養に来ていたピアニスト、
エカチェリーナ・セルゲーイェヴナ・プロトポーポヴァと知り合う。 |
1862
(29) |
11月、バラキレフと知り合い、「力強い仲間(ロシア5人組)」に加わり、作曲法を学ぶ。
シューマンの音楽を知り、その影響の強い交響曲第1番の作曲に着手する。 |
1863
(30) |
1月、医科大学助教授就任。
9月17日、エカチェリーナ・セルゲーイェヴナ・プロトポーポヴァと結婚。 |
1864
(31) |
医科大学教授就任。 |
1867
(34) |
9月、モスクワ・ボリショイ劇場で歌劇『ボガトゥィリ』が上演される。
複数の歌曲を作曲する。 |
1868
(35) |
2月、交響曲第1番試演、パート譜の不備などから不評。
冬、ボロディンの書いた音楽批評論文が3本、新聞に掲載される。 |
1869
(36) |
1月、交響曲第1番、バラキレフの指揮により初演。
10月、スターソフから『イーゴリ遠征物語』のオペラ化を勧められ、『イーゴリ公』の作曲に着手する。 |
1870/10
(36) |
雑誌『ズナーニイェ』創刊。
以降1年間、編集委員を務める。 |
1872
(39) |
婦人医学講習会を後援、化学講師を務める。 |
1874
(41) |
医科大学化学主任就任。 |
1875
(42) |
夏、歌劇『イーゴリ公』の作曲を進める。 |
1876/4
(42) |
歌劇『イーゴリ公』の「ほまれあれ」(プロローグの民衆の合唱)、リムスキイ‐コルサコフの指揮により初演。 |
1877
(44) |
医科大学会員に選出される。
3月、交響曲第2番、ナープラヴニークの指揮により初演。
夏、ドイツにリストを訪問、親交を結ぶ。 |
1879
(46) |
歌劇『イーゴリ公』の「コンチャークのアリア」、
「ポーロヴェツ(だったん)人の踊り」、「(プロローグの?)最後の合唱」、
「ヤロスラーヴナの嘆き」、「ガーリチのヴラヂーミルのアリア」、
「ヤロスラーヴナと女たちの場面」、
リムスキイ‐コルサコフの指揮により演奏。 |
1880
(47) |
4月、交響詩『中央アジア(の草原)にて』、
リムスキイ‐コルサコフの指揮により演奏。
5月、交響曲第1番、ヴァイスハイマーの指揮により国外(ドイツ、バーデンバーデン)初演。 |
1881
(48) |
5月、ドイツにリストを訪問。
11月、ムソルグスキイの死を受け、歌曲『遠きふるさとの岸辺に寄せて』を作曲する。 |
1882
(49) |
ベリャーエフと知り合う。 |
1884
(51) |
3月、交響詩『中央アジア(の草原)にて」、ジャドゥールの指揮によりベルギーで演奏。
11月、交響曲第1番、グリンカ賞受賞。 |
1885
(52) |
夏、ドイツにリストを訪問。
ベルギーにメルシ‐ダルジャントー伯爵夫人を訪問、
アントワープの演奏会で交響曲第1番、第2番、『中央アジア(の草原)にて』
及び歌曲が演奏される。
冬、キュイと共に、ベルギー訪問。
リエージュ、ブリュッセルでの演奏会で交響曲第2番、『中央アジア(の草原)にて』、
『イーゴリ公』より「ヴラヂーミル・イーゴリェヴィチのカヴァティーナ」が演奏される。 |
1886
(53) |
12月、交響曲第3番に着手。 |
1887/2/27
(53) |
医科大学教授会主催の謝肉祭の仮面舞踏会で倒れ、帰らぬ人となる。 |